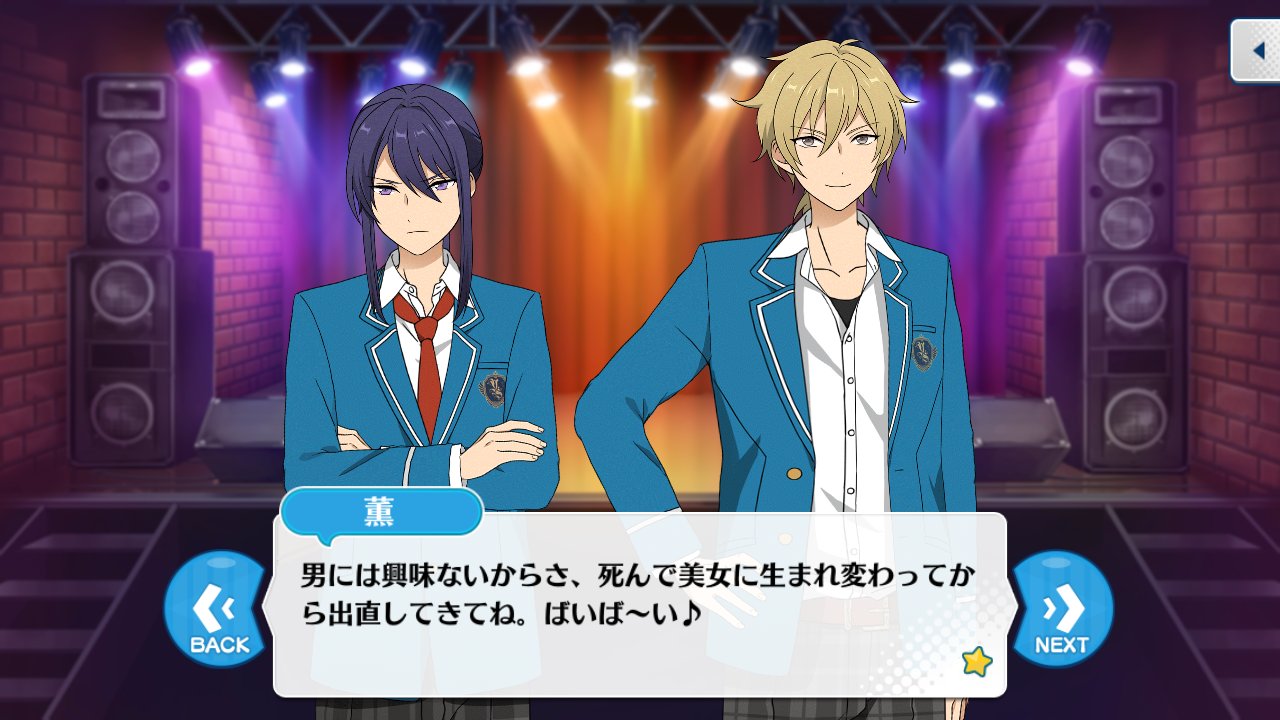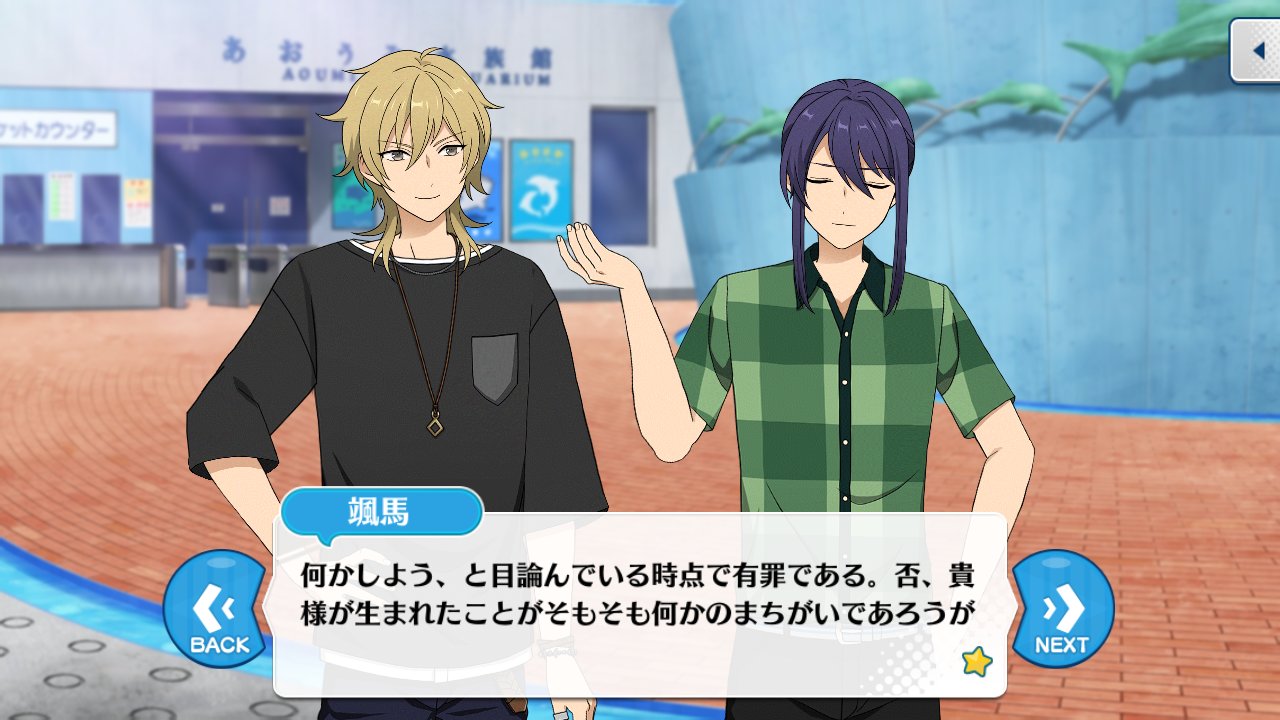薫&颯馬アンソロジー


生まれ変わって

はじめに
当サイトは2024年7月28日(日)発行予定の
「あんさんぶるスターズ!!」非公式ファンブック
『生まれ変わって出直せたなら』アンソロジー企画告知サイトです。
二次創作にご理解がない方の閲覧はご遠慮ください。
このアンソロジーは個人が企画・運営する非公式なものです。
原作者・関係企業・版権元等とは一切関係ありません。
生まれ変わってから
出直してきてね
貴様が生まれたことが
何かの間違いであろう
コンセプト
「死んで美女に生まれ変わってから出直して」
「生まれたことが何かのまちがい」
互いの存在さえも否定する言葉を
ぶつけ合ったあの頃から、
ずいぶん遠くまできました。
神崎颯馬の誕生日・4月20日と
羽風薫の誕生日・11月3日。
一年のうち最もその人の生が祝福の言葉で満ちる
誕生日という日、そのまんなかに、
あの頃から二人が描いた軌跡を
振り返るアンソロジーです。
企画概要

- タイトル
- 『生まれ変わって出直せたなら』
- 内容
- 薫と颯馬の暴言の応酬を思い起こすアンソロジー
- カップリング
- 薫颯・颯薫・リバ・友情その他諸々含みます。
- 二人の組み合わせ以外のカップルは含みません。
- 発行日
- 2024年7月28日
- サイズ
- A5版
- ページ数
- 124ページ
- 価格
- 会場価格¥1200
頒布情報
イベント
-
東京ビッグサイト 西1ホール ク42a